第1節 静寂の研究室
ラッパの夜から三ヶ月。
世界は、まるで巨大な機械が不意に電源を落とされたかのように、不自然なほど静まり返っていた。
物理的な破壊は何一つなかった。
ビルはそびえ立ち、道は舗装されたままで、雪はただ白く積もるだけだ。
だが、何かが決定的に失われていた。
人々が交わす言葉は熱を失い、視線はうつろに相手の背後をさまようようになった。
誰もが、自分の内側から響き続ける微かな残響音に耳を澄ませ、他者の言葉がそれに触れるのを恐れているかのようだった。
カイ・エルノは、その静けさの底で、さらに深い無音にこもっていた。
大学研究室の地下深くに設置された「防音室」。
分厚い防音材と鉛で覆われた壁は、外の世界の音も、そして内側の音も、一切通さない。
世界が「再構築の衝動」という名の熱病に浮かされる中、彼はただ一人、その衝動の源をコンソールの数値として「固定」しようと、モニターを睨み続けていた。
「暗騒音が下がりすぎている……」
カイは、世界中の観測所から送られてきた音響データを睨み、低く呟いた。
ラッパの夜以来、人間の経済活動が停滞した影響で、地球全体を覆っていた「文明のノイズ」が、観測史上ありえないレベルまで低下していた。
それは、まるで巨大な獣が呼吸を止めた後の静けさだった。
だが、カイが追っているのは、その「静けさ」そのものではない。
この静けさの底で、今もなお鳴り続けているはずの「何か」だった。
第2節 ラッパの夜(回想)
三ヶ月前のクリスマスの夜。
カイは、この防音室にはいなかった。
彼は街の灯りが見下ろせる、研究室の最上階にいた。
聖夜の鐘の音をサンプリングするためだ。
だが、彼の本当の興味は、鐘の音そのものよりも、その「響きが人々の感情にどう作用するか」という、いささか異端なテーマにあった。
深夜0時。古びた教会の鐘が、凍てついた空気を厳かに震わせる。
データは順調に記録されていた。
鐘の音が最後の一打を終え、その残響が夜空に溶けて消えようとした、まさにその瞬間だった。
──音がした。
それは耳で聞いた音ではなかった。
鼓膜を震わせたのではない。頭蓋の奥、あるいは胸骨の奥深くで、直接「鳴った」。
金属質のラッパ。
しかし冷たくはなく、むしろ熱を帯びた、透明な痛みのような響き。
分析機器の針は、一切振れなかった。
物理的な音波は存在しない。だが、カイは確かにそれを「聞いた」。
その響きは、彼が幼い頃、高熱に浮かされた日に聞いた「音」と酷似していた。
世界から切り離され、自分一人が熱の膜に包まれているような、あの孤独な感覚。
そして、その音は一つの記憶をこじ開けた。
『──探しなさい。音は、いつだってそこにある』
それは、母の口癖だった。
彼が音響学者になったのは、その言葉に導かれたからだ。
あるいは、縛られたからだ。
ラッパの音は、彼にとって「懐かしい痛み」──すなわち、母の残響そのものだった。
第3節 異端の系譜(回想)
カイの母、ミナ・エルノもまた音響学者だった。
だが、彼女の研究は学会の主流からは大きく外れていた。
「音響による記憶の共鳴」──それが彼女のライフワークだった。
『人の記憶は、固有の周波数を持っているのよ、カイ』
幼いカイの手を取り、彼女は古いピアノの鍵盤を叩いた。
『ド』の音。
『この音は、ある人にとっては“始まり”の音。
でも、別の人にとっては“終わり”の音かもしれない。
音そのものに意味はないわ。意味は、あなたの記憶が勝手に決めるの』
『でも、もし……すべての人間の記憶に共通して響く“鍵”となる周波数があったとしたら?
それは、失われた記憶を呼び覚まし、心の傷さえ癒せるかもしれない』
カイは、その研究発表会に連れて行かれた日のことを、今も鮮明に覚えている。
白髪の教授たちが、母の理論を「非科学的」「オカルトだ」と嘲笑する声。
冷たい視線の中、毅然と前を向いていた母の横顔。
子供心に感じたのは、母への同情ではなく、科学者たちの「理解力の欠如」に対する苛立ちと、母への誇りだった。
だが、その母は、ある日突然、失踪した。
『音は、いつだってそこにある』という言葉と、解読不能な数式が書かれたノートだけを残して。
カイは、母を異端視した学会を見返すために、科学者になった。
彼は、母の理論を「幻想」ではなく「仮説」として証明しようとしていた。
彼は、母の残したアルゴリズムを密かに解析し続けていた。
それは、母の「幻影」を追う行為であり、同時に、母の「呪縛」から逃れるための、彼自身の戦いだった。
第4節 波形の解読
回想が、防音室の冷たい空気で霧散する。
カイは、目の前のスペクトルアナライザに意識を集中させた。
あの日、世界中で同時に「観測不能な音」として記録された異常データ。
カイはそれを、母の理論を応用し、可聴域外の膨大な電磁ノイズの中から「抽出」することに成功していた。
「ありえない……」
今、モニターが描き出している波形は、音響学の常識では説明不能なパターンだった。
可聴域を遥かに超えた高周波と、ゼロに近い超低周波が、まるでDNAの二重螺旋のように絡み合い、矛盾したハーモニーを奏でている。
物理法則を無視した、ありえない「音」だ。
カイがこの解析に執着するのは、単なる科学的好奇心からではない。
この異常な波形こそが、失踪した母の研究──あの「異端の系譜」──と不気味に一致していたからだ。
彼は震える手で、母の残したアルゴリズムを起動する。
それは、あらゆるノイズの中から「意味のある響き」──母が「記憶の周波数」と呼んだもの──をフィルタリングするための、常識を逸脱したアルゴリズムだった。
彼は、ラッパの夜に抽出した波形データを、そのアルゴリズムに流し込んだ。
第5節 シータ波の発見
モニターがノイズを吐き出し、画面が激しく明滅する。
高負荷に耐えきれず、冷却ファンが唸りを上げた。
防音室の中では、冷却ファンの微かな唸りだけが現実を主張していた。
やがて、ノイズの嵐が収まり、一つのパターンがゆっくりと再構成され始めた。
それは、教会でサンプリングした鐘の音でも、自然界のどの音とも似ていなかった。
「これは……」
カイは息を呑んだ。
それは、人間の脳が特定の記憶を想起する際に見られる「シータ波」のパターン。
それも、極めて深く、個人的な記憶──
幼い日に、高熱の中で聞いた母の子守唄。
初めて「死」という概念を理解し、覚えた喪失の痛み。
それらと酷似した、生々しい記憶の波形だった。
「ラッパの音は、音ではなかった。それは……集合的な『記憶』そのものだ」
理性の最後の砦が、音を立てて軋む。
母の理論は、正しかったのか?
いや、それ以上に恐ろしい仮説がカイの頭をよぎる。
もし、この「音」が、世界中の人間の無意識下に眠る「個人的な記憶」を一斉に呼び覚まし、共鳴させたのだとしたら?
彼は、目の前の波形の中に、まだ科学では名付けられていない「何か」の輪郭を見た。
それは、彼が科学者として最も恐れ、そして息子として最も求めていたもの──
母の残響だった。

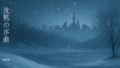
コメント