第1節 雪の街路
レナ・ヴォルトは、雪に覆われた街路を歩いていた。
ラッパの夜から三ヶ月、世界から熱と共に「音」が失われたように、街は静まり返っていた。時折すれ違う人々は、誰もが分厚いコートの下に、さらに厚い「沈黙」をまとっている。視線は決して交わらない。誰もが、自分の内側で響き続ける「何か」に捉えられている。
レナもまた、その「響き」に導かれるように歩いていた。
だが、彼女の場合、それはカイ・エルノのような知的好奇心からではなかった。それは、失った「支え」の代わりに、今や彼女の存在をかろうじて繋ぎ止めている、唯一の「鎖」だった。
かつて彼女は、神の静寂の中に救いを求めた。だが、ラッパの夜、彼女が拠り所にしていた神は、音もなく消え去った。
神を捨てた彼女に残ったのは、自由ではなかった。それは、より深く、冷たく、主体を失った「虚無」だった。
第2節 孤児院の祈り(回想)
レナの記憶にある最も古い「音」は、孤児院のシーツが擦れる、乾いた音だった。冷たいリネンの感触と、隣のベッドの子供の寝息。そして、自分がなぜここにいるのか、なぜ自分だけが愛されないのかという、答えの出ない問い。
それが、彼女の「罪」の原風景だった。生まれ落ちたこと自体が、何かの罰であるかのような、根源的な負い目。
「祈りなさい、レナ」
「神は、赦しを乞う者を愛してくださいます」
彼女は教えられた通りに祈った。凍える指を組み、冷たい床に膝をつき、「罪」の赦しを乞うた。毎晩、毎晩。
いつしか「祈り」は、彼女の呼吸そのものになった。神の静寂は、彼女の孤独を優しく包み込む毛布のように感じられた。信仰は、彼女がこの世界に存在する「理由」を与えてくれる、唯一の支えだった。
「罪」があるから、自分は祈る。祈るから、神は自分を見ていてくださる。
その秩序立った関係性だけが、彼女を世界の虚無から守っていた。
第3節 教会の崩壊(回想)
三ヶ月前のクリスマスの夜。レナは、もちろん教会にいた。
世界が終末を迎えるという噂がSNSを駆け巡り、多くの信徒が最後の審判に備えて身を寄せ合っていた。古い賛美歌が、恐怖と期待の入り混じった声で礼拝堂に響いていた。
深夜0時。鐘が鳴り終わり、司祭が厳かに聖書を掲げた、その時だった。金属質のラッパの音が、耳ではなく、魂に直接突き刺さった。
信徒たちはパニックに陥り、「神よ!」と叫ぶ者、床に突っ伏して泣き出す者で溢れかえった。
だが、レナは違った。彼女は、教会の冷たい床に膝をついたまま、動けなかった。彼女の胸の奥で、確かに「声」がしたからだ。
それは、司祭が語る神の声でも、シスターの優しい声でもなかった。それは、紛れもなく、レナ自身の声だった。
──赦しなさい。
(はい、神よ。私の罪をお赦しください)彼女は、いつものように心の中で祈った。
──違う。
声は、厳しく響いた。
──神ではない。あなたが、あなた自身を赦しなさい。
その瞬間、レナは理解してしまった。
自分を縛っていた「罪」とは、神が与えたものではなかった。自分が「愛されない」という恐怖から、自分自身で作り上げ、必死に抱きしめていた「枷」だったのだと。
そして、自分が生涯を捧げて祈ってきた「神」とは、その「枷」を正当化するために生み出した、壮大な「不在」という名の虚像に過ぎなかったのだと。
長年彼女を支えてきた信仰の柱は、蝋燭の炎が消えるように、音もなく崩れ去った。
神は、どこにもいなかった。
救いは、天から降ってくるものではなく、この凍てついた胸の内で見つけるしかないのだと、知ってしまった。
彼女は、泣き叫ぶ信徒たちを背に、よろめきながら教会を去った。
第4節 邂逅
神を捨てたレナは、今、どこへ向かえばいいのか分からなかった。「赦し」の主体を失った今、彼女の「罪」(という名の虚無)は、行き場もなく、以前より重くのしかかる。
もし、神に赦される以外の方法で自分を赦すとしたら、それは一体、どうすればいいのか?
彼女は「神以外の何か」を求めて街を彷徨った。あのラッパの夜以来、微かに耳の奥に残る「響き」──。
それは、教会で聞いた賛美歌よりも、ずっと弱く、か細い音だった。だが、不思議と「途切れない」音だった。それだけが、彼女の唯一の道標だった。
その響きに導かれるように、彼女はある研究所の前にたどり着く。雪が降りしきる中庭で、一人の男が、まるで天からの啓示でも待つかのように、パラボラアンテナのような奇妙な集音器を空に向けていた。
それが、カイ・エルノだった。カイは「ラッパの音」の残響を、今も世界に満ちているはずの「記憶の波」を捉えようと、機材のダイヤルを神経質に調整していた。
「……何か、聞こえるのですか?」
レナは、まるで自分自身に問いかけるように、呟いていた。
第5節 二つの欠落
カイは機材から目を離さず、警戒するように鋭く答えた。
「……なぜそう思う」
「ラッパの音」の調査だと近づいてくる者は、この三ヶ月で大勢いた。神の啓示だと騒ぐ狂信者か、政府の陰謀だと喚く者、あるいは単なる野次馬。彼はそのすべてに辟易していた。
だが、レナの問いは、彼らとは違っていた。
「私にも、聞こえるから」
彼女は、カイの横顔を見つめたまま、続けた。
「それが何なのか、知りたくてたまらない。……それが、私をここに連れてきたから」
カイは初めて彼女を見た。その目には、狂信も、好奇もない。
そこにあるのは、自分と同じ──あるいは、自分とは質の違う、だが同じ深さの──「欠落」からくる、切実な渇望だった。
彼女は「答え」を求めているのではない。「理由」を求めているのでもない。ただ、その「響き」の正体を知らなければ、息もできない、というような切迫感があった。
「……ノイズだ」
カイは、自分に言い聞かせるように呟いた。
「世界が壊れた、ただのノイズだ。文明活動が停止して、静かになったから、普段は聞こえない地磁気か何かが干渉しているだけだ」
「ノイズ……」
レナは、その言葉を反芻した。
「あなたは、そうやってそれを『理解』しようとしているのね」
「当然だ。俺は科学者だ」
「私は……」
レナは俯き、凍える手で胸元を押さえた。
「私は、祈ることをやめた。あれが、神の声ではないと知ってしまったから。でも、神でないなら、あれは一体、何だったの……?」
カイは、彼女の問いに答えなかった。答えられなかった。
彼は、彼女の瞳の奥に、自分が最も恐れているもの──「理解」を超えた何かを、盲目的に「信じる」ことでしか生きられなかった人間の、脆さを見た。
そしてレナは、彼の瞳の奥に、自分が最も渇望していたもの──「信仰」という名の逃げ道を、冷徹な「理性」で必死に塞いでいる人間の、孤独を見た。
二人の間を、雪が静かに落ちていく。
世界から失われた「熱」の代わりに、二つの「欠落」が、凍てつく空気の中で、微かに共鳴し始めていた。

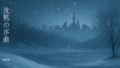
コメント