第1節 機能停止した都市
「再構築」は、社会の機能を静かに麻痺させた。
ラッパの音は人々の「内なる声」を増幅させ、その結果、人々は「外なる声」に応える衝動を失った。
命令、ニュース、広告、義務、あるいは単なる世間話──他者から発せられるそれらの「音」は、今や自らの内なる響きを乱すノイズでしかなくなった。
テレビ局は放送を止めた。
ラッパの音を「分析」しようとした技術者やコメンテーターたちが、その周波数に触れ、次々と職場を放棄したからだ。
今や画面に映るのは、分析に失敗した残骸のような砂嵐か、あるいは「沈黙」を推奨する無意味なテロップだけだった。
物流も止まった。
トラックの運転手は、荷物を運ぶ「義務」よりも、幼い頃に見た空の青さを思い出す「衝動」を選んだ。
スーパーマーケットの棚からは商品が消えたが、人々は略奪すらしなかった。
飢えの苦痛よりも、他者と奪い合うことで生じる「不協和音」を恐れたからだ。
街は物理的にではなく、社会的に「瓦礫」と化した。
人々は互いの「内なる響き」が干渉しあい、不協和音を生むことを無意識に恐れ、視線を合わせず、最小限の言葉、あるいは言葉を全く介さずに離散した。
誰もが自宅という名の防音室にこもり、自らの「欠落」と静かに対峙する、内向きの冬眠に入っていた。
第2節 特異点へ
カイとレナは、そんなゴーストタウンと化した街を、奇妙な二人組として歩いていた。
研究所での出会いの後、カイはレナを追い払おうとした。
彼の「観測」に、彼女のような「信仰を失った不安定な変数」は邪魔だったからだ。
だが、レナはカイの機材が捉える微弱な「ノイズ」──彼女が「響き」と呼ぶもの──に、正確に反応した。
「……今、強くなった。あなたには分からないの?」
カイの機材の針が、レナの言葉の直後に、わずかに振れた。
偶然ではない。彼女は、カイの最高精度の機材よりも敏感に、「音源」の揺らぎを感知していた。
カイは科学者としてのプライドを捨て、レナを「生体センサー」として利用することを決めた。
レナは、カイを「響きの正体を知る手がかり」として、彼に従うことを決めた。
二人の目的は、異なっていた。
カイは、解析した波形が示す「最大特異点」──ノイズの発生源であり、母の研究の核心に触れる場所──として、そこを目指していた。
レナは、自分を導く「響き」が、一つの「祈り」ではなく、無数の「救いを求める声」が集まる場所だと直感したから。
二人の目的地は、皮肉にも一致していた。
機能停止した都市の中心部。
かつて金融センターと呼ばれ、世界で最も多くの「欲望」という名のノイズが交錯していた場所だった。
第3節 ノア
雪が、意味を失った紙幣と共に舞っていた。
割れたガラス窓が並ぶ高層ビル群は、まるで巨大な墓標だ。
止まった電光掲示板が、虚空を照らしている。
「……ここだ」
カイが呟き、測定器の感度を上げた。
「ノイズレベルが異常に高い。まるで嵐の中心だ」
「いいえ」
レナが震える声で遮った。
「嵐じゃない……静かすぎる。何も、聞こえない……」
レナにとっての「響き」が、この場所でだけ、完全に途絶えていた。
その「静寂」の中心に、一人の子供がいた。
金融ビルの吹きさらしのエントランス。
大理石の床に、ただ座っていた。
10歳ほどに見えたが、その瞳は生まれたての赤子のように、あるいは千年生きた老人のように、何も映していなかった。
ただ、二人の存在に反応して、小さく身じろぎするだけだった。
言葉はない。薄い衣服一枚で、寒さも飢えも感じていないかのようだった。
レナの唇が、無意識に震えた。
彼女が探し求めていた「響き」の答えが、こんなにも無垢で、空っぽな存在であることに、彼女は打ちのめされた。
「……ノア?」
聖書に登場する、大洪水と再構築の象徴。
なぜその名が口を突いて出たのか、レナ自身にも分からなかった。
第4節 鏡
カイはレナの感傷的な呟きを無視し、即座に「観測対象」として行動した。
「危険だ、下手に近づくな」
彼は衝動的に、高感度集音マイクと測定器をその子供──ノア──に向けた。
「被検体、性別不明、年齢推定10歳。バイタル……」
瞬間、機械が金切り声を上げた。
ヘッドフォンをしていたカイの耳を、凄まじいハウリングが襲う。
測定器の波形が、振り切れた。
「ぐっ……ぁっ!」
だが、それは物理的な音ではなかった。
ノアが、カイの理性の奥に隠された「欠落」──母への渇望と、母の研究を信じたい自分を否定する「理性の壁」──を無理やり引きずり出したのだ。
『──カイ、探しなさい。音は、いつだってそこにある』
母の幻聴が、頭の中で何千倍にも増幅されて響き渡る。
「やめろ……やめてくれ!」
それは「懐かしい痛み」などではなかった。
それは、彼の科学者としての自我を破壊する、暴力的な「共鳴」だった。
カイは激しい頭痛に膝をついた。
一方、レナは、カイの苦痛を目の当たりにしても、動けなかった。
彼女は祈るようにノアに近づいていた。
助けようとしたのではない。
この「虚無」の正体を見届けなければ、彼女は前に進めなかった。
レナは、雪に濡れたノアの冷たい手を、両手で握った。
その瞬間、ノアの口から、初めて白い息が漏れた。
光の粒子のように見えた。
だが、レナが感じたのは「癒し」ではなかった。
『──赦しなさい。あなたが、あなた自身を』
ラッパの夜に聞いた、あの内なる声。
しかし今、彼女に響いたのは、それだけではなかった。
孤児院の冷たいシーツの感触。
シスターの冷淡な視線。
「罪」を抱きしめていた幼い自分。
神を捨てた虚無感。
そのすべてが、何の解決も得られぬまま、何の慰めも与えられぬまま、ただ冷たく、そこにあることを「肯定」された。
それは、痛みを伴う「受容」だった。
ノアは、カイの「理性」を増幅させて苦痛を与え、レナの「虚無」を増幅させて受容させた。
ノアは鏡だった。
彼が「人類の無意識から生まれた」のか、「何者かによって送られた」のかは、誰にも分からなかった。
ただ、彼は人々の“欠落”した部分をありのままに映し出し、共鳴させる存在だった。
第5節 保護
カイは、数分間の記憶を失っていた。
気づいた時、彼はレナに肩を支えられていた。
例の子供は、レナの隣で、相変わらず虚空を見つめている。
「……何をした」
カイはレナを突き放した。
「あの子供は……何だ?」
「わからない」
レナは、まだ自分の手の感覚を確かめるように、指を見つめていた。
「でも、この子……響きの『答え』じゃない。この子自身が、響きそのもの……」
カイは頭痛をこらえ、冷静さを取り戻そうと努めた。
「危険すぎる。正体不明の周波数源だ。すぐに当局……いや」
彼は言葉を止めた。
「当局」は、もはや機能していない。
「……研究所に連れて行く。俺が分析する。あれは『音』だ。観測可能で、解析可能な、ただの現象だ。そうに決まってる」
それは、科学者としての彼の最後の強がりだった。
彼は「理解」できないものを「理解」可能な範疇に押し込めるために。
レナは、この子供を「知る」ために、カイの提案を受け入れた。
二人が彼を置いて歩き出そうとした瞬間、ノアが自ら立ち上がり、レナのコートの袖を、言葉もなく軽く掴む。
二人は、まだ言葉を発しないノアの手を、それぞれ左右から握った。
社会的に「瓦礫」と化した都市の中心で、科学者と元・信者の女が、人類の「鏡」である子供の手を引いて歩き出す。
それは、誰にも観測されることのない、新しい世界の、奇妙な始まりだった。

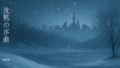
コメント