第1節 鐘楼への道
カイが母の「声」を受け入れ、その「非科学的な選択」に安堵したかのように、深く息をついた、その時だった。研究室の無機質なアラートが、けたたましく鳴り響いた。
「……侵入者だ」
カイが監視モニターに目を走らせる。
「ミラとは違う……この紋章、聖庁だ!」
モニターには、黒い制服に身を包んだ、ルーベンの「浄化」部隊が、研究所のゲートを破って雪の中を進んでくる姿が映っていた。目的は、彼らの言う「異端」──ノアだ。
「レナ!ノアを連れて防音室の奥へ!ここで食い止める!」
カイは、解析機材をバリケード代わりにしようと動いた。
だが、レナは動かなかった。彼女は、アラートの赤い点滅に照らされながら、じっとノアを見つめていた。ノアもまた、静かにレナを見返している。
「レナ、何を……」
「……聞こえる」レナが呟いた。「あのラッパの音よりも、もっと歪んで、苦しい響きが」
「敵の音か?」
「いいえ」
彼女はゆっくりと首を振った。
「あの鐘楼で、たった一人で震えている人の音。……ルーベン司祭の、絶望の音が」
彼女は、ノアの瞳に、かつての自分を見た。
秩序にすがり、赦しを乞い、それが得られないと知るや、今度は恐怖に震える、孤独な姿。
「カイ、ノアをお願い」
「どこへ行く!奴らと鉢合わせするぞ!」
「行かないと」
レナは研究室のドアに手をかけた。
「私は、あの人を『赦す』ことはできない。でも……あの人の『恐怖』は、私が一番よく知っているから」
それは、彼女が「神」を捨て、「虚無」と向き合った者として、果たさねばならない最後の「対話」だった。
第2節 対決
聖庁の大聖堂は、ルーベンの狂信的な部隊が出払ったため、不気味なほど静まり返っていた。ただ、鐘楼の頂上からだけ、ゴーン、ゴーン、と不規則で狂った鐘の音が響いていた。
レナが息を切らして駆け上がると、そこには、ロープに狂ったようにしがみつき、たった一人で鐘を鳴らそうと踠くルーベンの姿があった。
「鳴れ……鳴ってくれ!神の声を!秩序の音を、もう一度!」
だが、彼の力では、巨大な鐘はまともな音を立てない。ただ、重い金属がぶつかる鈍い音が響くだけだ。
「……もう、その音は鳴りません」
レナが静かに声をかけると、ルーベンは弾かれたように振り返った。その目は恐怖と疲弊で赤く充血していた。
「……貴様か」
彼はロープを放し、よろめきながらレナを睨みつけた。
「信仰を捨てた裏切り者め。悪魔に魂を売ったか!」
「悪魔はいません。あなたが聞きたくない『声』があっただけ」
「黙れ!」
ルーベンは祭壇に置かれていた儀式用のナイフを掴み、レナに向けた。
「お前も、あの子供も、秩序を乱す『音』だ!神が沈黙された今、この私が、お前たち異端を『浄化』する!」
第3節 殺意と受容
レナは震えていた。目の前にいるのは、かつて彼女が「神」として崇め、その言葉だけを「秩序」として生きてきた、絶対的な存在。だが今、その神の代理人は、ナイフを震わせ、自分自身の「恐怖」に怯える、ただの弱い老人だった。
その瞬間、レナの中に、熱く、黒いものがこみ上げてきた。それは「赦し」ではなかった。
(殺したい)
明確な「殺意」だった。自分を縛り付けた「秩序」への憎悪。自分を「罪人」として孤児院に置き去りにした、この理不尽な世界そのものへの憎悪。そのすべてが、目の前の老人という「象徴」に向けられた。
だが同時に、レナは、目の前の老人の「恐怖」に、かつて神にすがるしかなかった自分自身が、痛いほど共鳴しているのを感じていた。
──この人も、私と同じだったのだ。「混沌」が怖くて、「不在」が耐えられなくて、「神」という名の秩序に、必死でしがみついていただけなのだ。
彼女は、震える足で一歩、踏み出した。ナイフの冷たい切っ先が、レナの喉元に触れ、血が一筋流れる。彼女の瞳に、熱く黒い「殺意」が宿る。だが、彼女が次の瞬間に握りしめたのは、ナイフの柄ではなく、ナイフを握るルーベンの、恐怖に凍える「手」そのものだった。
レナは、涙を流しながら、はっきりと言った。ルーベンの瞳が、驚きに見開かれる。
「私を苦しめた、あなたの信じる神を。……そして、そんなあなたに今、殺意を抱いている、この私自身を」
「……何を、言って……」
「でも」
レナは、ナイフを握るルーベンの、インクで汚れた冷たい手を、自らの両手で、強く包み込んだ。
切っ先が、さらに皮膚に食い込む。
レナは、ルーベンを「赦す」ことも、自らの「殺意」を「否定する」こともしなかった。ただ、血が滲む喉元で、その震える手を、自分ごと包み込むように、強く、強く握り返した。
第4節 二度目の響き
その瞬間、世界中で、二度目の音が響いた。
それはラッパの音ではなかった。
それは、カイが「幻聴」を「選択」した音だった。
それは、ミラが「観察」を捨て、「介入」を選ぼうと娘の番号を必死に押す音だった。
それは、レナが「殺意」と「赦せない心」を抱えたまま、目の前の「恐怖」を包み込んだ音だった。
人々が、自らの「醜さ」と「欠落」を否定せず、解決もせず、ただ、その痛みを伴ったまま「引き受ける」と決めた瞬間に発せられた、内なる「共鳴音」だった。
ゴーン、と。
ルーベンが鳴らそうとして鳴らなかった鐘が、まるで自ら鳴ったかのように、深く、厳かな、しかし新しい音色を響かせた。
ルーベンは、ナイフを落とし、その場に崩れ落ちた。彼の「秩序」は崩壊した。だが、彼を包んでいた「恐怖」もまた、レナの体温と共に、鐘の音に溶けていった。
選別は、終わった。裁きによってではなく、それぞれの「選択」によって。

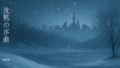
コメント