第1節 プロトタイプ
カイ・エルノの研究室は、今や要塞と化していた。ノアを保護してから三日。カイはノアを解析するため、レナはノアを「理解」するため、二人はこの防音設備が整った地下研究室に立てこもっていた。
だが、その束の間の静寂は、無機質なノックによって破られた。
「カイ・エルノ博士ですね。国家再建調査局のミラ・サーンと申します」
防弾ガラスの向こう側に、一人の女性が立っていた。薄いダウンジャケットにスラックスという軽装だが、その目だけが、この機能停止した世界に似つかわしくないほど冷静な光を宿していた。彼女の後ろには、聖庁とは明らかに制服の違う、武装した調査官が二人控えている。
ルーベンが「浄化」の指令を出す一方、政府の残存機能もまた、この「特異点」を察知していたのだ。
「何の用だ。ここは大学の管轄だ」
カイがインターコム越しに威嚇する。
「その『大学』はもう機能していません」
ミラは淡々と事実を述べた。
「あなたが保護している『特異事象』……コードネーム『ノア』の身柄を引き取りに来ました」
「ノアは『事象』じゃない!」
レナがカイの隣で叫んだ。
ミラはレナを一瞥し、わずかに眉をひそめた。
「感情的な反応は、分析のノイズになります。……博士、ご理解ください。私たちは、その子供を『社会的再教育の原基』として分析し、この機能停止した社会を『制御』する必要があるのです」
「制御だと?あいつは制御できるような代物じゃない!」
カイは、自分が体験した幻聴の苦痛を思い出し、叫んだ。
「だからこそ、です」
ミラは、カイがロックを解除するのを待たず、調査官に特殊なカードキーを使わせた。分厚い防音扉が、重い空気の音を立てて開かれる。
第2節 観察者の鎧
ミラは、カイとレナを調査官に任せ、一人でノアのいる防音室へと入った。ノアは、カイが用意した簡易ベッドの上で、ただ窓の外の景色を見ていた。
「……はじめまして、ノア」
ミラは、かつて彼女が最も得意としたフィールドワークの時と同じ、冷静で、対象に警戒心を抱かせない声色で話しかけた。彼女は、ラッパの音によって世界が「感情の混沌」に陥ったことを、誰よりも嘆いていた。社会学者として、彼女は常に「感情の介入」が物事をいかに破壊するかを研究してきた。
その信念は、彼女の私生活によって、苦い形で証明されてもいた。
──『ママは、私を見てない!私を……私を“観察”してるだけじゃない!』
数年前、思春期の娘が、泣きながら彼女にそう叫んだ日があった。夫と離婚し、仕事に没頭していたミラは、娘が抱える友人関係の悩みを、まるで論文のケーススタディのように「分析」し、「客観的な解決策」を提示してしまったのだ。
娘が欲しかったのは「解決策」ではなく「共感」だった。「介入」を恐れ、「観察」に徹した結果、娘は心を閉ざし、ラッパの夜が来るずっと前から、二人の関係は「機能停止」していた。
だからこそミラは、この世界的な「感情の暴走」を鎮圧するため、ノアを「観察」し、「理解」し、「制御」しなければならないと固く信じていた。
第3節 介入の恐怖
「さて、ノア。君が何者なのか、記録させてもらう」
ミラはアタッシュケースから小型の心音計と携帯脳波計を取り出した。
「身体的な苦痛は与えない。ただ、あなたの『反応』が見たいだけ」
彼女が心音計の冷たいセンサーを、ノアの薄い胸にそっと当てた、その瞬間だった。
(ドクン、ドクン、ドクン……)
彼女の耳に装着されたイヤホンから響いたのは、ノアの心音ではなかった。それは、彼女自身の、恐怖に加速していく心音だった。
「違う……」
ノアが、初めてか細く、しかしはっきりと呟いた。
「あなたは……“観測”しているのではない」
ノアの虚無の瞳が、初めてミラを捉えた。
その瞳に、泣き叫ぶ娘の顔が、ありありと映り込んでいた。
『──ママは、私を観察してるだけ!』
鼓動が、彼女の理性を破壊するメトロノームのように鳴り続けた。
心音が、耳元で破裂しそうになる。
「……あなたは」
ノアの唇が、ミラの心の声を代弁する。
「“介入”を、恐れているだけ」
センサーを装着した瞬間、鉄の匂いがあの日の記憶を呼び起こした。
パリン、と。ミラの理性を守っていた「観察者の鎧」が、音を立てて砕け散る。娘への罪悪感、切り捨てたと信じていた後悔、そして「共感」という名の混沌とした感情が、目の前のノアの姿を借りて、一気に溢れ出した。
「あ……あ……」
彼女は心音計を取り落とし、よろめくように後ずさった。
第4節 切断された回線
「……今日の調査は、中止します。ですが、あの『原基』は社会秩序の制御に必要です。必ず、回収に戻ります」
ミラは、防音室から転がり出るなり、調査官たちにそう告げた。彼女の顔は青ざめ、完璧だったはずのポーカーフェイスは崩壊していた。
カイとレナが、呆然と彼女を見ている。
「対象は、厳重に隔離。ただし、我々が戻るまで、手は出さないように。……博士、これは『命令』です」
彼女はそれだけ言い残し、部下と共に慌ただしく研究室を去った。
雪が再び降り始めた中庭を横切りながら、ミラは震える手で衛星電話を取り出した。
「介入を、恐れている……」
ノアの言葉が、脳内で反響する。
彼女は、娘の番号を呼び出そうとした。あのラッパの夜以来、一度も連絡が取れていない、別居した娘の番号を。
だが、指が止まる。今、電話して、何を言えばいい?「ママは間違っていた」と?「あなたのことを分析していた」と?そんな感情的な「介入」をして、また娘に拒絶されたら?
いや、それ以前に──。
(ピッ、ピッ、ピッ……)
呼び出しボタンを押すが、返ってくるのは電子的なエラー音だけ。社会インフラの麻痺は、彼女の特権的な回線にさえ及び始めていた。
切断された回線──それは、彼女と娘を繋いでいた最後の線でもあった。
ミラは、雪の中で立ち尽くした。「観察」という名の安全地帯から引きずり出された彼女は、今や、不器用な「参加」を選ぶしかない、凍てつく荒野に立たされていることを知った。
彼女の息が、白いノイズのように宙に溶けた。

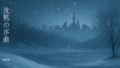
コメント