第1節 ノアという触媒
ミラ・サーンが嵐のように去った後、研究室には再び、重い静寂が戻ってきた。カイは、調査官が荒々しく開けた防音扉を睨みつけ、舌打ちした。ミラの「制御」という言葉が、彼の耳にこびりついて離れない。
「……結局、同じだ」
カイは、防音室の中で相変わらず虚空を見つめているノアに目を向けた。
「理解できないから『制御』する。ルーベンとかいう司祭は『浄化』する。……俺がやっている『解析』も、結局は同じことか?」
レナが、静かに首を振った。彼女は、カイが投げかけた言葉ではなく、カイの内なる「焦り」に応えていた。
「あなたは……知りたがっているだけ。私も同じ」
彼女はそっとノアのそばに寄り添い、その冷たい手を握った。カイには理解できない、穏やかな表情だった。レナのその「受容」する姿が、カイの「理解」への渇望をさらに苛立たせた。
彼は解析装置の前に乱暴に座り直す。だが、モニターを見て息を呑んだ。
ノアがこの研究室に「保護」されて以来、異常なノイズを発していた解析アルゴリズムが、ミラの訪問を境に、まるで嵐が過ぎ去ったかのようにクリアな状態に安定していたのだ。
いや、安定したのではない。ノアという存在が、ラッパの夜の膨大なノイズデータの中から、カイが最も求めている「一つの記憶」だけを、強力な触媒のように濾し取り、浮かび上がらせていた。
ノアが、ミラの内なる「娘」の声を増幅させたように、今度は、カイの内なる「母」の声を、増幅させようとしていた。
第2節 母の声
カイは、何かに憑かれたようにキーボードを操作した。母が残した、あの狂気的な方程式。ノアによってフィルタリングされた、純粋な「記憶の波形」。
二つが結合し、再構成が始まる。
(ザー……)
スピーカーから、ホワイトノイズが響く。そのノイズが、次第に一つの周波数に収束していく。それは、カイが幼い頃に聞いた、母が研究室で使っていた古いテープレコーダーの起動音と酷似していた。
そして──
『カイ……』
息が止まった。それは、紛れもなく、失踪した日の朝に聞いた、母の声だった。機械越しではない、暖かく、少し掠れた、あの声。
『……探さなくていい。私は、あなたの中にいる』
涙が、自分でも気づかないうちに頬を伝っていた。会いたかった。この声が聞きたかった。かつて観測したあの冷たい「シータ波」のデータではない。暖かな「記憶」そのものが、今、彼の鼓膜を震わせている。
母は、自分の研究が正しいと伝えたかったのか?自分を捨てたことを、謝りたかったのか?
第3節 幻聴との対峙
だが、歓喜が頂点に達した次の瞬間。科学者としてのカイの理性が、氷のように冷たい声で、彼の内側で囁いた。
『──本当に?』
全身の血が、逆流するような感覚。これは、本当に「母の声」か?
カイの解析によれば、ラッパの音は「集合的無意識」の暴走だ。そして、目の前にいるノアは、ミラの時に証明されたように、対象の「欠落」を読み取り、それを増幅させる「鏡」だ。
ならば、今、彼が聞いているこの声は──。「ラッパの音」がカイの記憶を読み取り、ノアという「増幅器」を通して、カイの理性を融解させるために作り出した、完璧な「幻聴」なのではないか?母の研究が正しかったと「思わせる」ための、甘美な罠なのではないか?
「……違う」
カイは頭を抱えた。
「これは……これはデータだ。俺の脳が作り出した幻覚だ……」
「──違う、これはまだ現象だ。錯覚ではない」
「理解」できないものを「受容」することへの、本能的な恐怖。この声を受け入れてしまえば、自分はもう「観測者」ではいられなくなる。ミラのように、あるいはルーベンのように、狂気に堕ちる。
第4節 非科学的な「選択」
彼は震える手で、解析コンソールの「全データ削除」のキーに指をかけた。この幻聴は危険だ。ノアも危険だ。すべてを消去し、この研究室を閉鎖し、すべてを「なかったこと」にしなければならない。
だが、その指が、止まった。
彼は、防音室の中で静かにノアの手を握るレナを見た。彼女は、神という絶対的な「理解の枠組み」を失った。それでも、彼女は目の前の「理解不能な存在」を拒絶せず、ただ、そこに「共にいる」ことを選んでいる。
彼は、狼狽しながら去っていったミラを思い出した。彼女は「理解」に固執するあまり、「介入」を恐れ、娘との関係を「切断」した。
「理解」とは、一体何だったんだ。自分は、母の理論を「理解」しようとして、母の言葉を「解析」しようとして、結局、母の「心」を理解していたか?
母が学会で嘲笑された日、自分は母を誇りに思った。だが、その「誇り」は、母の孤独に寄り添うものではなく、ただ自分の「理性」を満足させるためのものではなかったか?
『……探さなくていい。私は、あなたの中にいる』
スピーカーから、声が繰り返される。それが幻聴かどうかなど、もはやどうでもよかった。
彼はスピーカーから繰り返される母の声に目を閉じ、次の瞬間、その指でコンソールのメイン電源スイッチを、強く押し下げた。
すべての解析データが音もなく消え、静寂が戻る。それは音響学者としてのカイが、自らの「理解」を「殺した」瞬間だった。彼は電源の落ちたコンソールに額をつけ、嗚咽を漏らした。
彼は「理解」を放棄したのではない。「理解」を超えたものを、それが幻聴である可能性ごと、引き受けるという「選択」をした。
それは、彼にとって最も非科学的な「選択」であり、母の「呪縛」から解放され、初めて息子として「母の記憶」を受け入れた瞬間だった。
カイが顔を上げると、防音室のガラスの向こうで、ノアが彼をじっと見つめていた。その瞳が、ほんのわずかに、微笑んだように見えた。

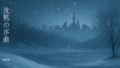
コメント