第1節 ノアの消失
二度目の響きが世界を満たしたあの日、カイの研究室に駆けつけた「浄化」部隊は、困惑したように武器を下ろしていた。彼らの内なる「響き」もまた、彼らの「敵意」や「義務」を融かし、ただ立ち尽くさせていた。
そして、その中心にいたはずの存在──ノアの姿は、どこにも見当たらなくなった。
カイが「幻聴」を受け入れ、レナが「殺意」を包み込んだ、あの共鳴の瞬間に。カイとレナが部屋に入ると、そこだけがありえないほど暖かく、シーツには彼が座っていた大理石の床の冷たい感触だけが残っている。
彼がその役目を終え、世界そのものに溶け込んだのか、あるいは、元いた場所へ帰ったのか、それは誰にも分からない。
ただ、ミラの調査局が回収した機材には、『対象消失。ただし、周辺のノイズレベルは完全に沈静化』とだけ、記録が残された。
第2節 再構築された世界
世界は再構築された。だが、それは美しいユートピアではなかった。
ラッパの夜がもたらした「内なる声」は、今やかつてのように人々を麻痺させるものではなく、日常の背景音のように、ただそこにあるものとして受け入れられていた。
インフラはゆっくりと回復したが、テレビは以前のように声高に「正解」を叫ぶことはなくなり、ただ静かに、必要な情報だけを流すようになった。
人々は相変わらず誤解し、傷つけ合い、古い言葉の残骸に躓いていた。
ただ、ラッパの夜以前と決定的に違うことが一つだけあった。
人々は「静寂」を恐れなくなった。
会話の途中で言葉が途切れても、無理に言葉を継ごうとはしなくなった。その沈黙の中で、相手が何を「言わなかった」のか、その内なる響きに耳を澄ませようとするようになった。
「共鳴」しようと、「理解」ではなく「受容」しようと。それは、痛みを伴うが、確かな再生の音だった。人々は歩み始めた。
第3節 森の静寂
カイ・エルノは、音響学者の職を辞した。彼は今、森の奥深く、かつて母が研究に使っていた古い山小屋で、レナと共に暮らしている。
彼は、母の「声」の正体を、未だに「理解」してはいない。あの「幻聴」は、二度目の響きの後、次第に小さくなり、今ではほとんど聞こえなくなっていた。
だが、時折、風が木々を揺らす音の中に、それが微かに混じることがある。カイはもう、それを疑わない。解析しようとも思わない。
それは彼の「静寂」の一部になった。
彼は今、ラッパの音ではなく、レナが淹れるコーヒーの湯気や、雪が解ける水音といった、名もなき「音」を観測している。
第4節 終わらない対話
レナ・ヴォルトは、祈ることをやめた。彼女は、ルーベンを「赦した」わけではない。
二度目の響きの後、ルーベンは聖庁から追放された。彼は「秩序」を乱した者として、今や自らが「異端」の烙印を押されたのだ。
彼は今、国境近くの小さな村で、未だに「神の秩序」を説こうと踠いている。だが、その声に耳を傾ける者は、もう誰もいない。
レナは、月に一度、その村を訪れる。薬と食料を運び、何も言わずに去ろうとするルーベンの背中に、静かに声をかける。
「司祭、あなたの聞きたかった音は、まだ見つかりませんか」
ルーベンは、決して彼女を「赦さず」、苦虫を噛み潰したような顔で彼女を睨みつける。
レナもまた、彼を「赦さず」、ただ、その震えが、かつての自分の祈りと同じリズムであることに気づきながら、彼の手を見つめ続けた。
それは「赦し」という名の安易な終着ではなく、痛みを伴う、終わらない「対話」だった。
第5節 不器用な参加
ミラ・サーンは、調査局を休職し、娘と共に暮らし始めた。ラッパの夜以来、初めて再会した娘は、ミラを「観察」するのではなく、ただ泣きじゃくる母親を見て、戸惑いながらも、その背中をさすった。
「介入」を選んだミラの日常は、摩擦と失敗の連続だ。娘が何を考え、何を求めているのか、彼女には「理解」できないことばかりだ。
それでも彼女は、かつてのように「分析」しようとはせず、ただ、娘と同じテーブルで、不味いコーヒーを飲みながら、その「理解できなさ」に、不器用に参加し続けている。
第6節 始まりの音
ラッパの音は、裁きではなかった。それはただ、世界に満ちていた「記憶」が、凍てついた人々を融かし、互いの「欠落」の形を照らし出し、新しい関係性を紡ぎ出すための、壮大な序曲だったのである。
ノアは消えた──そう公式の記録にはある。
けれど、ときどき雪の降る夜の夢の中で。カイが、レナが、ミラが、そしてルーベンさえもが。
大理石の床に座り、白い息を吐くあの子が、静かに笑うのを見るのだという。
それは、恐れながらも聴き続けることを選んだ、すべての人間が鳴らす、「始まりの音」だった。

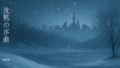
コメント